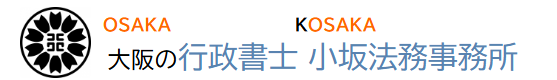建築士事務所の登録
建築士事務所の登録(更新)
建設業許可申請
建設業は、建設工事の完成に対して対価が支払われる請負業のことです。
建設業法では建設工事の内容によって業種が29種類に分類されています。
一式工事は建築一式工事と土木一式工事の2種類で、専門工事は27種類もあります。
一式工事は、複数の下請企業を元請企業が統括して大規模な工事を行うときの、元請企業が原則取得する許可になります。
一式工事の許可を受けているからといって、それぞれの専門工事を単独で請け負うことができるわけではないことに要注意です。(名前からややこしい。)
建設業の許可は知事許可と大臣許可があります。(請負金額が小さいものばかりを請け負う企業は許可が不要な場合があります。)
営業所の所在が単一の都道府県の場合は知事許可、複数の都道府県にまたがる場合は大臣許可が必要になります。
建設業の許可は下請に出す金額などによって、一般建設業許可か特定建設業許可の必要な許可が変わります。
一般建設業許可は工事を下請に出さない場合、もしくは下請に出す場合は1件の工事代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に取得し、特定建設業許可は前記の金額を超える場合に取得します。
許可申請の際に法人の場合は個人の場合と異なり、役員や出資者に関する書類も提出を求められるようになります。
建設業許可申請の「新規」とは、新しく建設業の許可を受けようとすることをいい、次の3つがあります。
- 新規
- 建設業者が初めて許可を受けようとする場合
- 許可替え新規
- 大臣許可を受けている建設業者が新たに知事許可を受けようとする場合
- 知事許可を受けている建設業者が新たに大臣許可を受けようとする場合
- 知事許可を受けている建設業者が引っ越して、別の都道府県の知事許可を受ける場合
- 般・特新規
- 一般建設業許可のみを受けている建設業者が新たに特定建設業許可を受けようとする場合
- 特定建設業許可のみを受けている建設業者が新たに一般建設業許可を受けようとする場合
建設業許可申請の「更新」とは、すでに受けている許可を5年ごとに更新する手続きをいいます。有効期限の30日前までに行う必要があります。
建設業許可申請の「業種追加」とは、現在許可を受けている業種とは別の業種について許可を受けることです。
建設業の許可を受けるには5つの要件があります。
- 経営業務管理責任者がいること
- 経営業務管理責任者になるには一定の地位や経験年数が必要です。
- 営業所ごとに専任技術者がいること
- 専任技術者になるには一定の学歴・資格や経験年数が必要です。
- 誠実性があること
- (法人の場合)法人、役員、支配人、営業所の代表者を含みます。
- (個人の場合)事業主、登記された支配人、営業所の代表者を含みます。
- 財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 一般建設業と特定建設業で異なり、特定建設業のほうがより厳しい条件になっています。
- 欠格要件に該当しないこと
許可申請書を管轄の窓口に提出して、不備なく受理されてからの審査の標準処理期間は知事許可でおおよそ30日、大臣許可でおおよそ120日となっています。
参考の外部リンク:大阪府の手引き
経営事項審査
国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者は必ずこの審査を受けなければなりません。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、この資格審査にあたっては欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化(総合点数)して順位・格付けが行われます。
この「客観的事項」にあたる審査が経営事項審査(経審)になります。
建設業法により、建設業許可にかかる許可行政庁が審査を実施することになっています。
経営事項審査の有効期間は、結果通知書を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月の間になります。
毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するために、毎年決算後すみやかに(決算終了後4か月以内を目安に)経営事項審査を受けておく必要があります。
(あらかじめ、決算変更届の提出を行う必要があります。)
下の式より、総合評定値を出すには経営状況分析結果が使われるため、経営事項審査の審査日までに順番的に経営状況分析を終えておかなければなりません。
「経営状況分析」結果(Y)+「経営規模等評価」結果(X・Z・W)=「総合評定値」(P)
経営状況分析申請は国土交通省に登録した登録経営状況分析機関に対して行います。
経営規模等評価申請と総合評定値請求は、経営状況分析結果通知書を受領後に、通常は2つを同時に許可行政庁に対して行います。
参考の外部リンク:大阪府の場合
入札参加資格審査
入札に参加したい法人や個人は、入札案件を発注する自治体や団体の入札参加資格を取得しておく必要があります。
審査では、反社会的勢力ではないこと、税金の滞納がないこと、案件を処理する実績や技術力を有すること、等々をチェックされます。
発注機関が個別に行う入札参加資格審査の受付期間は決められており(あまり長くないことが多い)、その受付期間内に必要書類を揃えて準備して、提出する必要があります。
また、入札参加資格を取得してからも、次のことに気を付けておく必要があります。
- 参加資格を継続させるための申請期限の管理
- 定期的に実施される申請等への対応
- 経営事項審査の継続的な受審
参考の外部リンク:入札参加資格審査申請 大阪府
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業の許可の要件は次の5つになります。
- 講習会を受講していること
- (公財)日本産業廃棄物処理振興センター実施の講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。(修了証の有効期限は新規は5年間、更新は2年間)
- 経理的基礎を有していること
- 適法かつ適切な事業計画を整えていること
- 収集運搬のための施設(車輌等)があること
- 欠格条項に該当しないこと
許可更新申請は5年ごとになります。
更新申請には更新講習会の修了証が必要になります。
「優良基準」に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定する「優良産廃処理業者認定制度」があり、その認定を受けると通常5年の許可の有効期間が7年になります。
「優良基準」は次の5つです。
- 遵法性
- 事業の透明性
- 環境配慮の取り組み
- 電子マニフェスト
- 財務体質の健全性
有効期間が長くなるほか、自治体ホームページで適合企業として公表されることで排出事業者が業務委託しやすい環境が整備されたり、許可更新の際の申請書類の一部を省略できるなど、メリットもあります。
参考の外部リンク:大阪府の場合
その他
その他のご相談も対応します。お気軽にご相談ください。
参考の外部リンク:
建築士事務所登録 大阪府の場合