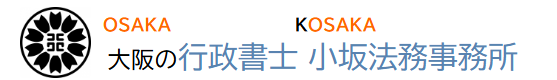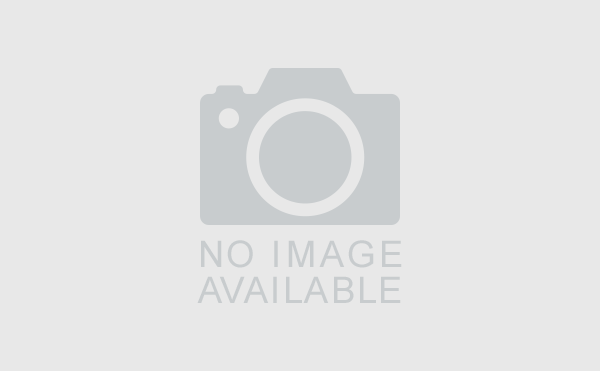警備業務の区分
警備業務とは、次のいずれかに該当するもので、他人の需要に応じて行うものを言います。(警備業法2条1項)
| 業務内容 | 警備業務対象施設 | |
| 1号業務 | 盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 | 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等 |
| 2号業務 | 負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 | 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所 |
| 3号業務 | 盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 | 運搬中の現金、貴金属、美術品等 |
| 4号業務 | 人の身体に対する危害の発生を警戒し、防止する業務 | 対象者の身辺 |
警備業を営むには、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。その申請は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に認定申請書を提出して行います。
認定の欠格要件は以下のとおりです。(警備業法3条)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
- 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
警備業の申請手続を行政書士に依頼することもできます。ご相談ください。