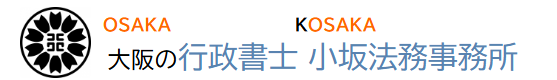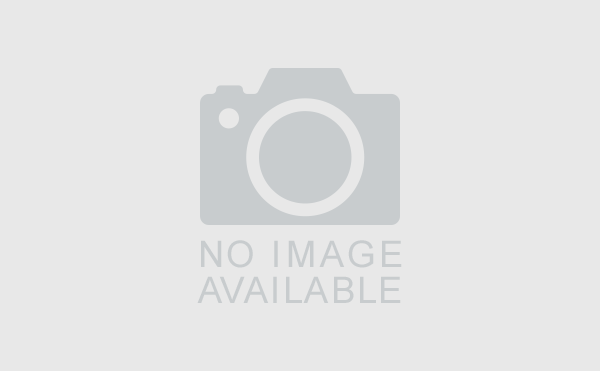いじめ防止対策推進法
いじめはやってはならない。
いじめたものは忘れても、いじめられたものは心身的に苦しい状態に追い込まれて、自分の存在を軽視するようになったり、その経験が後の将来にわたって長く尾を引いて影響を与え続けるものだ。
いじめ防止対策推進法というのがある。
これはいじめをしたものにペナルティーを与えたり、周囲の取り組みも混じえて対策するものだ。
国のいじめ撲滅への本気さが見えると思う。
ちょっとここで話がそれるが、刑法に触れておく。
刑法では犯罪に刑罰を科すには次の3つが全て揃う必要がある。
- 構成要件
- 違法性
- 有責性
構成要件は、各々の犯罪について要件が法定されており、その要件を充たしていなければ刑罰は科せられない。
違法性は、正当行為、正当防衛、緊急避難などの言葉をよく聞かれると思うのだが、法令または正当な業務による行為、急迫不正の侵害に対し、自分や第三者の生命・身体・財産などを守るために、やむを得ずにおこなう防衛行為、等で生じたものについては犯罪の要件を充たしていても、違法性が阻却される場合がある。
仮に違法性が阻却された場合は、犯罪の構成要件を充たしていても、刑罰に科せられない。
有責性は、違法行為をしたことに基づいて行為者を非難できることをいう。
例えば精神上の障害がある場合で心神を喪失しているものは、犯罪に対する刑罰を科して更生を促すことは困難で、どちらかいうとその人にとってはその期間で刑罰より治療を受けることが必要とされる。
そのため刑罰に科せられなくなる。
これら3つが揃わないと、国家による刑罰権で処罰されることはない。
自由が保障されているのである。
話をいじめ防止対策推進法へと戻すが、この法律ではかなり幅広くいじめと捉えられるようになっている。
被害者の心証次第なところがある。
ここが冤罪の発生の可能性が生じる怖い部分と筆者は感じている。
刑法では要件を充たしても、違法性阻却事由に当たらないかや、有責性が審議される。
一方、いじめ防止対策推進法では、いじめと捉えられてテーブルに乗せられると、否応なしに対策が進められることになる。
万人、好きな人もいれば、片方では苦手な人もできてくる。
それでも、みんな苦手な人ともふだんはうまくやっている。
しかしどこかのタイミングで不幸にも煙が上がる事がある。
大人の世界でも〇〇ハラという言葉がいまやどこでも聞かれ、回避するために意識せざるを得ないくらい日常語になっている。
子どもたちの世界でも、苦手な相手というのは何がしかできてくるだろう。
それがなにかのタイミングで不幸にも燻って執念に変わることもある。
そのときに、このいじめ防止対策推進法は冤罪を生む可能性はないだろうか。
阻却事由の審議方法の規定はない。
未成年者で反論するにも未熟でできないこともある。
今の制度ができたのは、世の中にひどいいじめ事件があったからなのは理解している。
それはまったく否定しない。
しかし、ある事案で煙が上がった際に、司法でもない、一機関の学校長や教育委員会が裁量で処理を進めるには、迅速に事案を処理できる一方で、誤った解決方法に進められてしまう危険性を完全に排除することはできないと思われるので、権限者にはそのようなところも意識して運用してもらいたい。