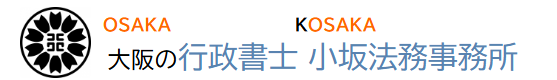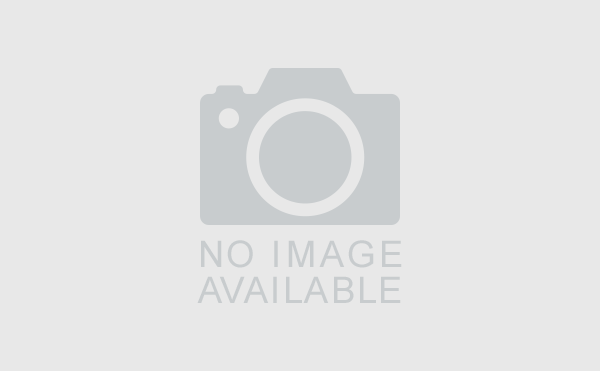共同相続における権利の承継の対抗要件
改正民法になってからは、遺言があっても、被相続人の意思が尊重されない承継が行われる可能性が生じています。今回はその話を以下でします。(防衛策もご紹介します。)
相続において相続人が、遺言があるのにあえて遺産分割協議などほかの方法によるというのでなければ、通常は遺言者の意思を尊重して相続がなされるはずです。それは改正民法でも同じです。
改正民法で気を付ける必要があるのは、遺言内容が「法定相続分を超える部分」がある相続で、かつ、第三者が関わってくる可能性がある場合です。その場合は、遺言者の意思を尊重するよりも、遺言内容を知りえない「第三者」が保護される内容になっています。
そのため、「法定相続分を超える部分」がある相続をする場合には、その各財産について相続開始後になるべく早い段階で対抗要件を具備すべく、手続きを済ませて防衛する必要があります。不動産については所有権移転登記を、預貯金債権については金融機関に確定日付のある証書でその旨の通知を行います。
例えば、被相続人には配偶者がすでになく、A、Bの2人の子がいたとします。被相続人の財産の中に土地が含まれており、遺言では土地はAに単独相続させるとしていました。しかしBはAの法定相続分を超過する部分も含めて、土地の1/2(Bの法定相続分にあたる部分)を第三者であるXに売り、所有権移転登記をしました。こうなると、XがAより先に対抗要件を具備するため、Aは後からXに対して対抗することができなくなります。
民法899条の2第1項
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
また、預貯金債権の場合は、同条2項により、先に内容証明郵便などで、確定日付のある証書で金融機関に通知する必要があります。
例えば、被相続人には配偶者がすでになく、A、Bの2人の子がいたとします。被相続人の財産の中に預貯金債権があり、遺言ではこの預貯金債権はすべてAに単独相続させるとしていました。しかしBには弁済期を超えた貸金債権者がおり、相続開始後に預貯金債権の1/2(Bの法定相続分)に対して差押えをすることも考えられます。そのようなケースではAが先に対抗要件を具備するために、内容証明郵便などの方法で、金融機関へ確定日付のある証書での通知を急ぐ必要があります。
民法899条の2第2項
前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
遺言があれば、被相続人の意思が表示されますので、相続人間ではその意思を尊重されると思われます。ただし、考えられる相続人の構成次第では第三者が関わってくる可能性がありますので、生前の遺言の手配だけでなく、相続開始後の各手続きについても、行政書士や司法書士(不動産登記の場合)などの専門家に依頼する方法も検討されることをお勧めします。