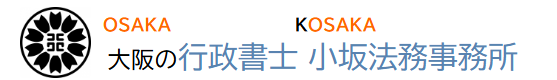在留資格取得
日本に上陸しようする外国人は、上陸審査を経て、在留資格を得る必要があります。
上陸のための条件は、次の4つがあります。(入管法7条1項1号~4号)
- 旅券・査証の有効性
- 在留資格にかかる条件
- 活動の真実性
- 在留資格該当性(入管法別表第1の下欄の活動、別表第2の下欄の身分・地位のいずれかに該当すること)
- 上陸許可基準適合性(入管法別表第1の2の表と4の表の在留資格については基準省令の上陸許可基準に適合すること)
- 在留期間(入管法施行規則3条に適合すること)
- 上陸拒否事由に非該当であること(入管法5条1項各号に非該当)
到着した空港、港での上陸審査において短時間で上記の上陸のための条件に適合することを証明することは困難なため、あらかじめ在留資格認定証明書を取得しておくことで、上陸審査の手続きを迅速に行うことができるようになっています。
在留資格認定証明書の申請は原則は外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して行う必要があります。しかし、実際には外国人本人が出頭することは困難なため、外国人を受け入れる予定の機関の職員が代理人として申請したり、本人や代理人の出頭に代えて地方出入国在留管理局に届け出た弁護士、行政書士等の申請取次者によって申請書を提出することもできます。
在留資格認定証明書が交付されると、それを国外にいる外国人に送付して、外国人が在外公館に持参して査証申請をし、査証を受けてから日本に到着した空港、港での上陸審査で在留資格認定証明書を提出して上陸許可を受けます。
在留資格認定証明書の交付申請の提出書類は、所属予定の機関の条件によってカテゴリ分けされていて提出書類が変わります。
書類作成がケースごとに変わり、複雑なことをご理解いただけると思います。
作成を行政書士にご依頼いただくことをお薦めいたします。
参考の外部リンク:出入国在留管理庁
在留期間更新許可申請
在留資格を有して在留する外国人は、原則、付与された在留期間に限って、日本に在留することができます。
しかし、その在留期間では当初の在留目的を達成することができない場合もあります。
その場合は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と認めるに足りる相当の理由があるときは、外国人が在留の継続をできるように在留期間を更新する手続きがあります。(入管法21条)
日本に在留する外国人が、付与された在留期限を超えて、現に有している在留資格に属する活動を引き続き行おうとする場合は、在留期間更新許可申請をすることができます。
申請は住所を管轄する地方出入国在留管理局に必要書類を提出して行い、時期は現に有する在留期間の残りの期間がおおよそ3か月以内になる時点以降に受理されます。(3か月以内の在留期間で決定されている場合は、おおよそ半分以上経過した時点以降に受理されます。)
在留期間更新許可の要件は次の2つです。
- 在留資格該当性
- 更新を適当と認めるに足りる相当性
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること(中長期在留者)
手続きをせずに在留期間を経過して在留する外国人は、退去強制事由(不法残留)に該当しうるほか、不法残留罪で3年以下の懲役または300万円以下の罰金などに処されることがあります。
在留資格変更許可申請
在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格の活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来の在留資格を新しい在留資格に変更するために申請するのが在留資格変更許可申請です。
申請は住所を管轄する地方出入国在留管理局に必要書類を提出して行い、時期は在留資格の変更事由が確定したときから、在留期間満了日までの間に行う必要があります。
ただし、在留資格の変更事由が確定したということは従来の在留資格該当性が失われていることもあり、その場合に手続きを先延ばししてしまうと後の手続きで在留状況不良と評価されて影響することがありますので、すみやかに手続きされたほうがいいです。
在留資格変更許可の要件は次の2つです。
- 申請にかかる在留資格についての在留資格該当性
- 変更を適当と認めるに足りる相当性(基準省令の上陸許可基準への適合性を含む)
また、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」などへの変更の際には、「留学」の資格で在留していた期間の在留状況も審査されますので、ご注意ください。
- 学校の成績が著しく不良だったり、欠席率が高い
- 資格外活動許可を受けずに就労
- 資格外活動許可を受けていたが範囲外の風俗業務に従事
- 資格外活動許可を受けていたが時間制限(原則、週28時間まで)を超えて就労
在留資格に対応する活動以外の就労活動を「専ら」行っていると「明らかに」認められる場合は、退去強制事由に該当する場合があるほか、専従資格外活動罪として3年以下の懲役、禁錮または300万円以下の罰金に処される可能性があります。また、「専ら」「明らかに」でなくても、在留資格に対応する活動以外の就労を行った場合は非専従資格外活動罪として1年以下の懲役、禁錮または200万円以下の罰金に処される可能性があります。非専従資格外活動罪で禁錮以上の刑に処された場合は退去強制事由に該当する可能性があります。
帰化許可申請
帰化とは、外国人からの日本国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、法務大臣が許可を与えることによって、日本の国籍を与える制度です。
帰化の要件は次の6つです。
- 引き続き5年以上、日本に住所を有すること
- 年齢が18歳以上で、本国法によって行為能力を有していること
- 素行が善良であること
- 生計を営むことができること
- 国籍を有さず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 憲法を遵守していること
これらを確認できる資料を集めたり作成して、提出することで申請します。
また、そのほかにも、日本の国籍を取得した場合、選挙権や公務就任権なども取得することになるため、問題が生じないよう日本語でのコミュニケーション能力も見られます。
注意が必要なのは、帰化は行政手続法の適用除外になっており、基準が明示されておりませんし、上記の要件は最低限のもののみ示されており、要件を満たしたからといって必ず許可されるわけではありません。
大臣の裁量で許可することが可能と規定されていますので、政策的なところも影響すると考えられます。
一度不許可になると、次の再申請でやみくもに同じように申請しても、数撃てば当たって許可されることはなく、むしろ許可のハードルは上がって困難さが増してきます。
不許可が出てしまってから後で頭を抱えることになるより、始めから行政手続きの専門家である行政書士に相談、書類作成を依頼するほうが時間やコスト面で総合的に見て少なく済むこともありますので、行政書士のご活用を検討されてはいかがでしょうか。
参考の外部リンク:法務局
その他
その他のご相談も対応します。お気軽にご相談ください。