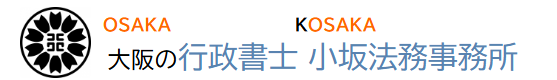相続
被相続人が亡くなると、相続人のために相続が開始し、次の調査が必要になります。
・相続「人」の調査
・相続「財産」の調査(負の財産である負債についても考慮が必要です。)
「人」の調査
相続人の調査では、相続人の範囲を確定させることが目的です。
被相続人の誕生から亡くなるまでの戸籍を集め、相続人を確認します。
被相続人が生前からこう話していたからこう思われるというのではその後の公的な手続きでは通用しません。
戸籍からひも解き、確認する作業が必要になります。
そして、それらを相続関係説明図にまとめます。
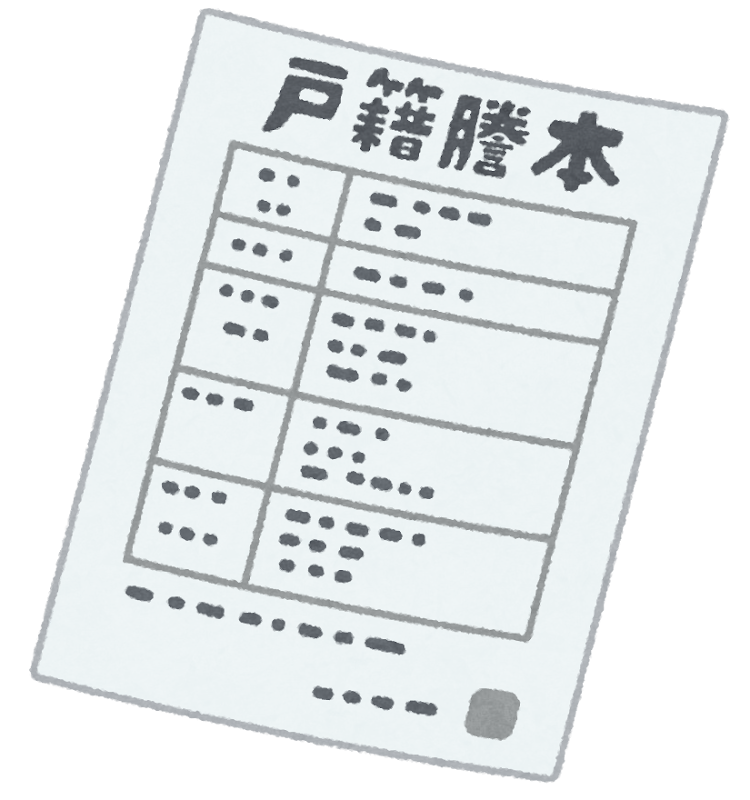
また、最近では法定相続情報証明制度という便利な制度もあります。
これは、相続関係を明らかにする法定相続情報一覧図を作成して、戸籍謄本等とまとめて登記所に提出することで、登記所の登記官が提出された法定相続情報一覧図が法律で定められた相続関係に合致しているかどうかを確認した上で、その法定相続情報一覧図に認証した旨を記載して、交付してもらうことができます。
この認証文の付与されている法定相続情報一覧図は、後々の金融機関での相続手続きや法務局での相続登記を行う際に、大量の戸籍謄本等の代わりに提出にすることができます。
提出書類が減りますし、複数枚交付してもらえるので、同時並行で手続きが進められるようになったり、それぞれの提出先で大量の戸籍謄本等を確認するのに要する時間を短縮することができ、メリットが大きいと思われます。
「財産」の調査
相続財産の調査では、被相続人にどのような財産があるかを確定し、相続財産目録にまとめます。
この情報は、相続放棄、限定承認、遺産分割協議、相続税申告、相続登記などの判断に欠かせないものです。
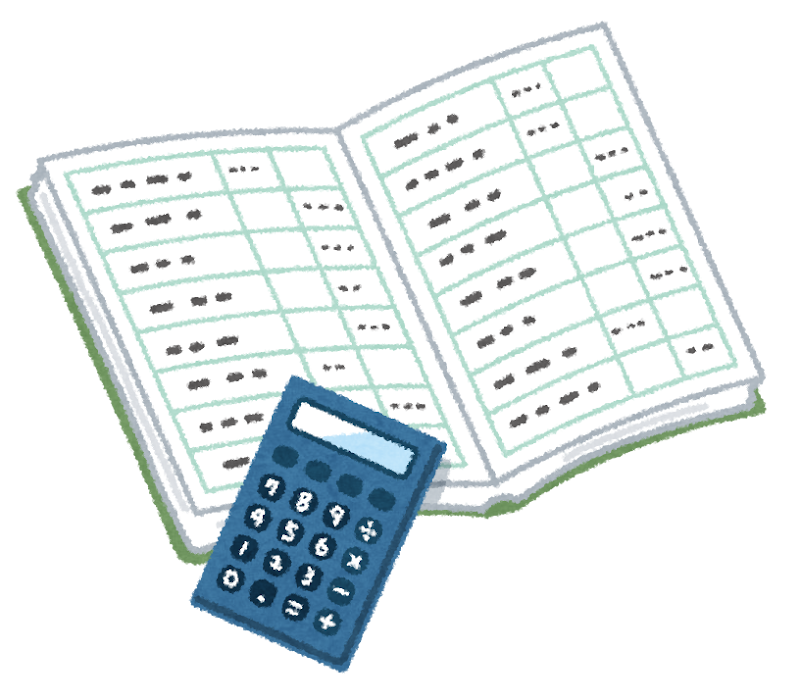
遺産分割協議書の作成
相続財産は遺産分割しないままだと、相続人で共同相続する形になります。
共同相続人は相続財産に対して法定相続分に応じた共有持分を持ちます。
共同相続のままで不動産などを放置しておくと、将来に処分する際に共有持分者の同意が必要ですがその持分者に相続が発生していた場合には同意を得なければならない人の数が増えていきますので、相続から早い段階で分割しておくことが一般的にベターと思われます。
遺産分割協議を実施して、まとまりましたら、その合意した内容で遺産分割協議書を作成します。

金融機関等での手続き
金融機関等で、認証文を付与された法定相続情報一覧図、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、等々の指示された書類を提出して、遺産の分割を行います。
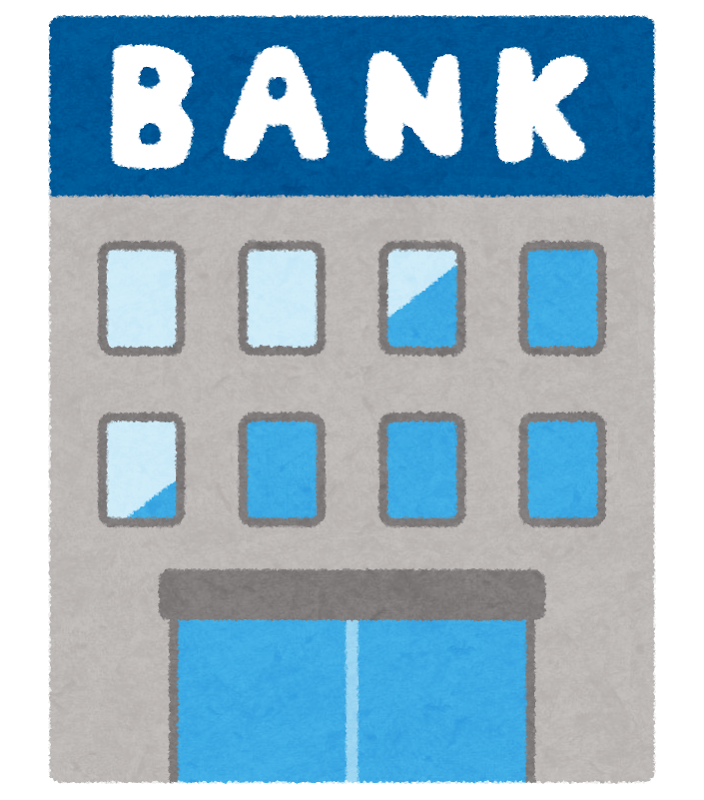
相続関係説明図(法定相続情報一覧図)、財産目録、遺産分割協議書の作成は弊所におまかせください。
弊所では財産額でなく、工数に応じて報酬額を算出させていただきます。
お見積りはお問合せください。
遺言
民法には、遺言の方式として、普通方式では3種類が規定されています。
自筆証書遺言
自筆で作成する必要があります。(財産目録のみ、目録各ページに署名押印すれば、パソコン等でも作成可能です。)
修正も要件をそなえれば可能ですが、誤った方法で修正すると無効になります。
費用は一番抑えられますが、将来に無効が判明する可能性があります。
法務局の自筆証書遺言保管制度を利用でき、周囲の人に制度を利用していることを伝えておくことで、遺言の存在を見落とされる可能性は低くなります。
自筆での作成が要件になっておりますので、弊所ではご依頼者様のご希望内容をお聞きして、文案を作成してサポートさせていただきます。

公正証書遺言
遺言者の口授したものを公証人が筆記し、公正証書の形式で遺言書を作成します。
公証人が厳格に作成しますの、将来無効になる可能性は小さい。
ただし、作成、修正ごとにコストがかかります。
遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失、偽造、変造のおそれはなく、証拠力は高いです。(裁判所での検認も必要ありません。)
周囲の人に公証役場に預けていることを伝えておくことで、遺言の存在を見落とされる可能性は低くなります。
弊所ではご依頼者様のご希望内容をお聞きして、内容の整理、公証役場との調整や、証人の手配を行います。

秘密証書遺言
自筆である必要はありません。
作成した遺言を、公証役場で公証人と証人2人の前で封筒に封して、公証人に封筒に追記してもらって作成します。
原本の保管は公証役場で行いません。
公証人のコストもかかりますが、内容を公証人が確認しながら書くわけではありませんので将来の開封段階で記載に不備が見つかって無効が判明する事例があったり、保管も公証役場で行いませんので将来見落とされる可能性もあり、コストの割に有効性が疑問視されてあまり使用されなくなっています。
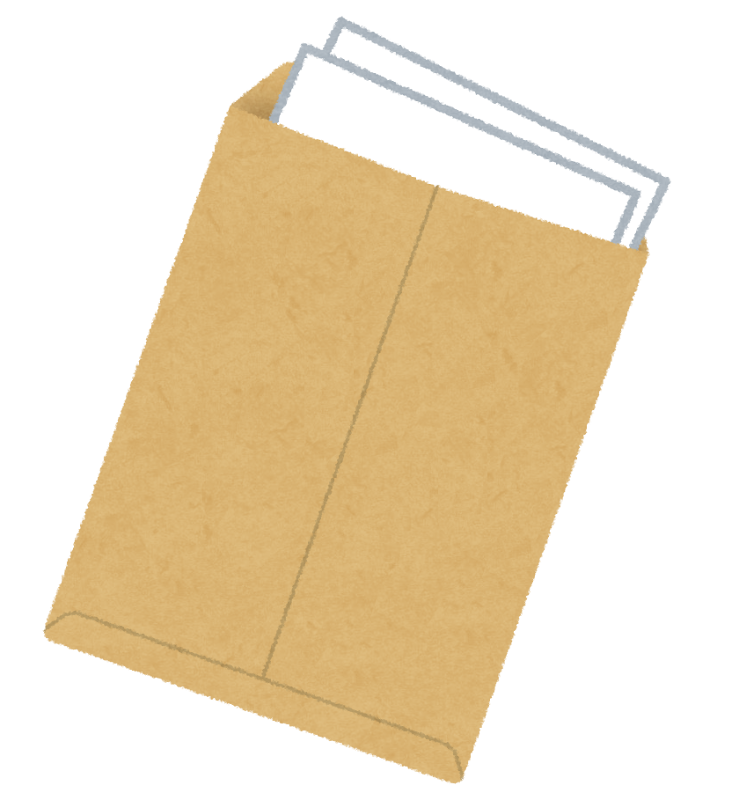
弊所では、財産額でなく、工数に応じた報酬額を算出させていただきます。
お見積りはお問合せください。