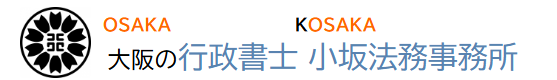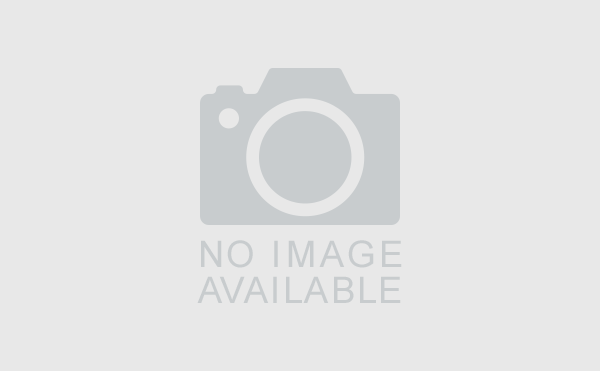裁量について
法律などの条文では「~することができる」のように、判断によってその法律効果を生じさせる可能性があるように書かれていることがあります。
これは、法律の目的を達成するために、すべてのパターンを網羅的に条項に規定することが難しい場合に、このような書き方をされていることが多いです。
この場合、その効果を生じさせるかどうかは、個々のケースで行政庁の意思や判断に委ねられることになります。
裁量では次の2つの点が行政庁に任されています。
要件裁量
法令等に規定されている要件を満たしているかどうかの判断を、その個別具体的な事案の処理にあたる処分権者に任せるもの
効果裁量
その法令等に規定されている効果の中で、どのような処分を下すかを処分権者に任せるもの
裁量があるからといって、行政庁が完全自由気ままにその決定ができるかというとそうではありません。
行政事件訴訟法30条に、行政庁の裁量処分が、裁量権の範囲を超え、またはその濫用があると認められる場合には、裁判所はその処分を取り消すことができるものとされています。
ここでも、取り消す「ものとする」でなくて、「できる」とされていて、裁判所にも裁量があってややこしいですが、行政庁の処分に対して司法が審査をして、取り消す可能性があるのです。
その司法審査の内容ですが、
- 法令等の目的・動機
- 平等原則
- 比例原則
- 信義則などの一般原則
- 考慮すべきことが十分に考慮されているかどうか
- 考慮すべきでないことが考慮されすぎてしまっていないかどうか
- 処分にあたって規定されている手続きが行われたかどうか
の面からチェックされることになります。
よって、行政庁に裁量が認められていても、なされる処分は公正、適正なところになってくるように仕組みができています。