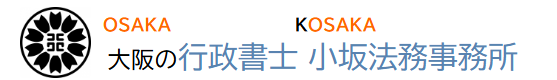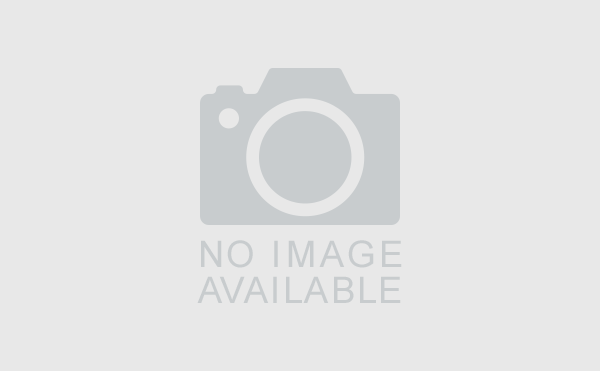遺言書の検認
遺言書には普通の方式で3種類あります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言(あまり使われていません。)
被相続人が亡くなって相続が開始してから、その後に遺言書が見つかった場合、開封には注意を要します。
実際にはそれが明確に遺言書と分かるように保管されていなければ、残されたご遺族様は何か分からずに中身を確認するために悪気なく、正しい手順によらずに開封してしまうかもしれません。
正しい手順によらずに遺言書を開封してしまうと、民法1005条で5万円以下の過料が課せられる可能性があります。
遺言書の保管者がある場合は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないことになっています。(民法1004条)
検認とは、関係する者が裁判所の指定する日時に集まり、遺言書の内容を確認します。
みんなで確認することで、その後に遺言書の内容に変更が加えられることを防ぎます。
遺言書の保管者がない場合は、相続開始後に遺言書らしきものを見つけた場合、開封して中身を確認しようとせず、家庭裁判所に提出して検認を請求するほうがいいです。
(もし検認で開封して中身が遺言書でない場合もあるかもしれないですが、その後の親族間の問題に発展しないように、正式な手続きを経るため、遺言書と推定されるものは個人で開けてしまわずに検認を請求しておくべきです。)
一方、公正証書遺言を作成されていた場合は、その原本は公証役場で保管されており、変更が加えられることがありませんので、検認の手続きは不要になります。
また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局に自筆証書遺言書の原本を保管している場合も、検認の手続きが不要になります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言を相続人が見つけた場合は、勝手に開封しないで家庭裁判所に提出、検認の手続きを経て家庭裁判所で開封しなければなりませんので、ご留意ください。