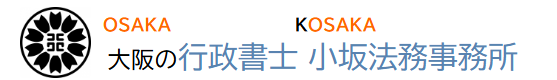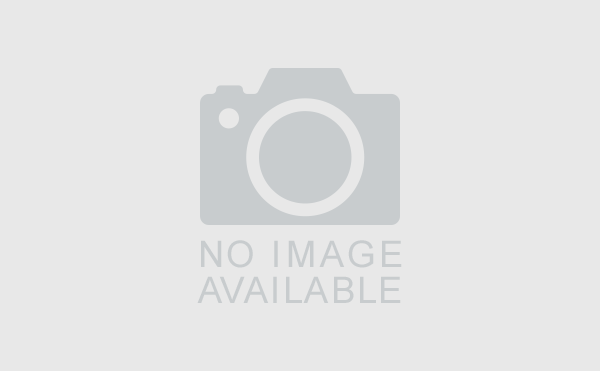取引基本契約での商法509条の排除
製造業者にとっては、製品を作れど作れど出荷されていくような状況は、作った製品が滞留して出ていかない状況よりは営業上好ましいです。
製造業者が注文書を受け取ったときに注文請書を返す運用にしている場合、忙しくなるとつい請書の返送が抜け落ちてしまうこともあるかと思いますが、今日はそのお話です。
民法上は、契約は一方の申込みに対して相手方の承諾があったときに成立します。
これを読むと、注文があったときに、請書を返さないと売買契約は成立していないように一見思われるのですが、これがビジネス(商行為)では変わってきます。
商行為では民法よりも商法の適用が優先され、そこに規定されていないことは商慣習に委ねられ、また商慣習に適当なものがないときに民法が適用されるように規定されています。
この優先順が曲者です。
商法では、リピートで受注するような間柄の場合、請書を返すのを忘れると、原則では売買契約が成立してしまいます。
在庫が潤沢にあって、出荷の準備ができていれば問題は少なく済むかもしれません。
が、もし、いざその製品の在庫はあまり積まれておらず、在庫繰りが厳しいし製造にかなりの期間がかかるような場合には、在庫繰りの確認等々でバタバタしている間に忙しくて先方との納期調整や請書の返送を忘れてしまうと(忘れてはいけないですが)、トラブルの元になる可能性があります。
リピートで受注するような間柄なら、都度の売買契約の締結は手間がかかるため、決まっている取引条件を取引基本契約書に落とし込んでしまう方法が取られます。
そこで、1つの対策の方法として、注文者からの注文書に対して、販売者が請書を交付することによって個別の契約が成立するように取引基本契約に入れ込んでおき、商法509条の適用を排除しておくような書き方にしておくこともあります。
行政書士は契約書などの権利義務に関する書類の作成を行いますので、ご相談ください。